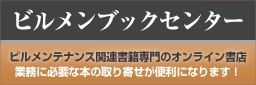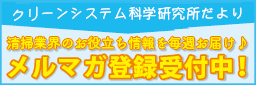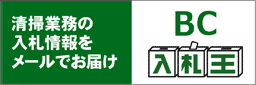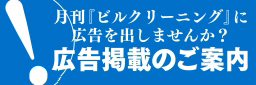ビルクリーニングを読む
業界の未来を考える〜業務編〜
ビルメンロボット戦略
清掃ロボット普及の第2ステージに向け発想の転換を
5年にわたる取材と東京協会の検証レポートから今後を考える
本特集はビルメンテナンス業界の最先端ロボットを通して、この業界のゆくえを想像してみることが主眼にある。清掃ロボットが普及しだして数年、新型コロナ終息後を考えれば、清掃業務のスタイルが激変し、清掃ロボットは必需品になっている可能性がある。
そんな将来を見据え、いま清掃ロボット導入について発想を転換しなければ、業界地図もがらりと変わるのではないか。そんな思いから、小誌が取材を通して見てきた清掃ロボット普及のための要点を整理したい。
折しも制作の途中、3月26日に(公社)東京ビルメンテナンス協会から「次世代における清掃ロボットの導入事例紹介レポート」が報告された。まずはこのレポートの概要を紹介するところから始める。
東京協会の検証レポートを読む
同協会のロボット検証プロジェクトは2017年度から始まっており、今回はフードコートやロジスティックセンターなどの新しい事例紹介のほか、中心メンバーでもある㈱小田急ビルサービスからは、「清掃ロボットに関する調査事業を振り返って〜更なるチャレンジ、未だ見ぬステージへ〜」と題するレポートも掲載されている。
このレポートから、清掃ロボットに対する業界の反応がうかがえるので、かいつまんで紹介する。
4年にわたった「清掃ロボットに関する運用実証」は、一貫して「清掃ロボットは労働力不足を和らげる有効策になりうるか」が目的だった。
2017年度は業務用の機器数台に焦点を当て検証を実施、2018年度は運用技術の確立、2019年度は導入への検討材料とするチェックリストの作成、2020年度はオフィスビル、大型ロジスティック施設、フードコートへの導入事例となった。
■ 2017年度
メーカー側も加わって検証。皮肉にもメーカー側と使用者側(ビルメン企業)間に清掃ロボットに求める性能について大きな乖離があることが明確になった。メーカー側は走行経路を設定し、スタートさせれば清掃ロボットが清掃してくれるので、結果的に人件費削減につながるとの説明だった。一方、使用者側はこの作業(仕上がり具合、作業時間、移動の手間、壁際汚れなど)は到底受け入れられるレベルではなかった。使用者側はメーカー側にさまざまな改良を要求。メーカー側はその要求を理解できなかった。
その理由として、メーカー側は異業種からの参入も多く、「清掃=単純作業」との思い込みが強かった。そもそもどのような状態が「清掃完了」なのかがわからない。加えて、清掃ロボットは高額でありながら、担当できる箇所は床面の一部にしか過ぎない。一部の作業に費用対効果を求めるには、単純作業だけでは不可能。
そこでメーカー側も、清掃業は単純ではないこと、清掃のコスト削減をするためには低価格化を実現しなければならないこと、メーカー推奨の「取扱説明(トリセツ)」を大きく見直さなければ使用者側に受け入れてもらうことは不可能であることの認識が芽生えた。
使用者側もまた、一方的な清掃ロボットに対しての批判的な立場を見直し、現時点の清掃ロボットの性能で何ができるか考えるようになった。
■ 2018年度
前年度の反省を踏まえ、運用技術の確立を目指し、共用通路はもとより専用部内も対象に検証を重ねた。これまで定説となっていた清掃ロボットと人はそれぞれ独立した作業を実施するのが効果的との説は大きく崩れ、両者は綿密に計算された関連性のある作業計画(マネジメント)がなければ、品質向上やコスト削減を期待することは困難であるとの結論に至った。
これまでの運用は清掃ロボットの性能に頼り切っていたが、これからは複数台を同時に稼働させるなどそれぞれの優位性からさまざまなシナジーを創造し、一定の運用技術を確立するに至った。
これにより、清掃ロボットは一定の条件が整えば導入可能との結果を得た。そこで、導入を検討しているビルオーナーや管理者等が、自己管理物件に導入できるか否かを事前に把握するため、簡易的な導入判定チェックリストを作成した。
■ 2020年度
オフィス、大型ロジスティック施設での検証。清掃作業は限られた時間内での作業完了が求められるが、労働負荷軽減を目指した清掃ロボットが作業前後に人力により移動させる手間が増えていた。また、保管場所には充電環境が整っていることが望ましい。これらを解決するため、建物設計段階からの導入計画、稼働時間を上げるため休憩時間帯での稼働、担当者不在時のオペレーションなどが報告された。
これまで従事者の無人化・少人数化を目指していたが、場合によっては操作、回収などをダイバーシティ化(人材の多様化)することにより、稼働時間の制約緩和やコストの削減へつながる方向性が見えてきた。
また、ハードフロアについては、カーペットと比較すると「壁際が苦手」な清掃ロボットで品質向上は困難との認識が改められた。壁際にほこりが堆積する前にロボットを稼働させることで、汚染の速度は鈍化し、美観維持が長時間となり品質向上につながったと考えられる。「汚れる前に清掃ロボットを稼働」というのが新たなスタンダードになるのではないかと感じた。
このように、複数年にわたり、清掃ロボットについてさまざまな角度から検証を行ってきた。当初の主な目的は労働力不足の解消だったが、昨今のコロナ禍のなか、消毒作業の無人化という要求に対しても、清掃ロボットへの期待は大きくなっているように感じる。新たな生活様式に適合するには低価格化は必須であり、排気管理など衛生面を含めた性能向上が求められるであろう。
これまでの検証で得られたキーワード、「建材の特性を生かす」「複数台同時走行」「マネジメント力は必須」「休憩時間帯での稼働」「ダイバーシティ化」「汚れる前に稼働」は決して不可能な課題ではなく、これまでの固定概念にとらわれない逆転の発想を含め、もう少し些細な発見があれば可能になるのではないか。
まず、4年にわたる継続的な検証に謝意を表したい。このレポートでは、検証を通してユーザーであるビルメン側と、供給側であるメーカー側が協働しながら課題を克服していく様子がうかがえる。清掃ロボットも、小型化、低価格化を含め、進化はあっても後戻りすることはないだろう。
清掃ロボット導入で求められる管理能力
清掃ロボットを論じるときによく聞かれるのが、性能、機能、品質という用語である。これも人との比較でよく語られる。しかし、ビルクリーニングの教科書をよく読めばわかるように、清掃業務には作業標準というものが欠かせない。作業計画には日常清掃と定期清掃があり、日常清掃は日々発生するほこりや汚れを軽い段階で早期に除去する役割があり、定期清掃は日常清掃では除去できない汚れを除去し美観を回復する役割とされる。
現時点の清掃ロボットは、あくまでも日常清掃が主体であり、設定された標準作業、つまり軽い段階の汚れ除去を遂行することが任務のはずである。ところが、前出の東京協会報告書のまえがきには、「清掃業は簡単な単純作業だけではなく、一種の職人芸に近い作業もある」とか、「清掃側の要求としては、汚れを自分の判断で見分けることができ分別することができる能力となる」などと述べており、「ロボット=万能」であらねばならないという観念がしみついていることがよくわかる。
性能や品質を言うのであれば、なぜ自動床洗浄機による作業の品質を検証しないのか。作業者の違いによる標準作業のバラツキを問題視しないのか。
清掃ロボットはあくまでもマシンであって、保有する能力で一定レベルの作業を行い、使用者はそれを評価し、必要に応じて運用面で改善を図る。つまり管理サイクルであるPDCAのうち、Dは人よりも標準作業を着実に実施してくれる。あとはCとAの繰り返しによって、運用効率を高めていくのが人の役割になる。
いまやだれでもパソコンを使うようになって、頻繁にバージョンアップが繰り返されるなかで、人はそれに慣れ、使いこなすために知恵を働かせる。
清掃ロボットも同様で、清掃機械の延長として捉え、限られた範囲のなかでどう運用し、使いこなせるかが鍵を握る。そのための運用ノウハウの確立と、管理者の育成こそが、さらなる清掃ロボット普及のためには欠かせない課題と思われる。